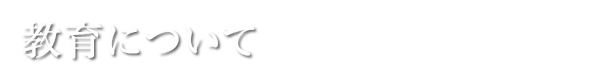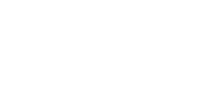研修医の方へ
留学生便り
国外
1. Queen Mary University of London, The William Harvey Research Institute
鎌田博之
皆様,ご無沙汰しております。2024年4月よりQueen Mary University of Londonにポスドクとして海外留学の機会をいただいております。ロンドンへ来て半年が過ぎ,海外で基礎研究を学び,実験を行える環境に大変感謝しております。私の勤務している研究所は,ロンドンの中心地にあり,同じQueen Maryにはヨーロッパ最大の心血管センターのバーツ心臓センターもあるため,心臓病研究が盛んに行われています。
私の所属するCentre for Microvascular Researchは,8つのグループ,約30名の基礎研究者(日本人は私含め3人,イギリス人が半数,その他多くはEU諸国出身)で構成されています。同副センター長でもある鈴木憲教授のご指導の下,心筋再生に関して研究を行なっています。渡英後,英国の動物実験ライセンスを取得し,実験に関するトレーニングを行なってきました。私のプロジェクトは,内科的に可能な新しい心筋再生医療を目指して,最適な細胞ソースや培養プロセスの検討,さらに動物実験で立証し,臨床応用につなげるという大きなプロジェクトになります。実験はまだ準備段階で,グループメンバーが少ない時期でもあり,また私にとって馴染みのないことばかりであるため,試行錯誤しながら頑張っております。
日常生活は,物価高,特に家賃高騰が悩みの種で苦労しています。米を含め日本食は特に高価ですので,じゃがいも(ベビーポテト美味しいです)を主食として生きています。また,現地の友人もでき,パブに飲みに行ったり(ビール好きになりました),週末はケンブリッジなどへ小旅行に行ったりしています。8月末には,ロンドンでESCが開催され,鹿児島から神田先生方が参加され,夕食をご一緒でき,大変励みになりました。来年は家族もロンドンに来る予定としているため,楽しみにしているところです。
大石教授をはじめとする医局の先生方には貴重な勉強の機会をいただいていることに大変感謝しております。少しでも多くのことを勉強し,鹿児島の医療に貢献できるよう頑張っていきたいと考えております。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
国内
1. 国立循環器病研究センター 研究所 分子薬理部
鮫島光平
ご無沙汰しております。2016年度入局の鮫島です。昨年に引き続き現況をご報告いたします。
現在私は大石教授のご厚意のもと,国立循環器病研究センター(以下国循)研究所分子薬理部で基礎研究に従事しております。
国循は日本に6か所あるナショナルセンターの一つで,大阪府吹田市岸部に位置し,病院はJR岸辺駅と直結しています。研究所は病院と隣接しており,2024年10月現在,17の研究室があり多くの著名な先生方が日々大きな成果を上げておられます。
私が所属している分子薬理部は,大阪大学大学院医学系研究科医化学教室出身で循環器内科医であられる新谷泰範先生が部長を務めており,連携大学院である大阪大学修士課程の学生さんや3名の室長の先生まで,総勢14名で構成されています。
現在,部内は複数のプロジェクトチームに分かれて研究を進めていますが,私は昨年度に引き続き,ヒト心筋症(特にミトコンドリア心筋症)に対して,シングルセルRNA解析や空間トランスクリプトーム解析(昨年度はVisiumというアッセイを使用しましたが,本年度は解像度が8μm四方に向上したVisium HDも実施しています)を用いて,病態解明や病勢推移を評価できるバイオマーカーの探索を行っています。2023年度は主にDryの研究が多かったのですが,幸いにも2024年10月現在,候補遺伝子を2つ選び出すことができ,現在は疾患モデルマウスでの発現を,免疫染色などで検証している段階です。また,昨年もお伝えしたように,時折大阪大学医化学教室に伺い,Extracellular Flux Analyzerを用いた化合物ごとの呼吸鎖活性の測定も行っています。さらに今年は新たに,他大学との共同研究として,ある疾患の病因候補遺伝子の表現型評価のためにマウス管理も行うようになりました。そこでマウスのエコーや組織回収,凍結切片作成,HE染色やMasson Trichrome染色,GenotypingのためのPCR,cDNA合成など一連の技術やマウスの交配など,新たに多くの経験を積んでおり,今年はよりWetな研究を行えています。
一方,学術発表については,上記の通りまだ候補遺伝子の検証段階であり,今後の展開が不透明なため,これまでの成果を発表する機会はありませんでした。来年度には論文化や発表を行えるよう,引き続き努力してまいります。
私生活においては,妻と二人の子ども(長女5歳,長男2歳)とともに大阪で生活しておりましたが,2023年12月に次男が誕生しました。関西には親族が少ないため,妻には大変な負担をかけており,感謝の気持ちでいっぱいです。そのため,今は臨床医時代と比べて朝や週末に時間的余裕があることもあり,部長や研究室の皆さまのご理解をいただきながら,家事や育児,家族のイベントにできる限り積極的に関わるよう心掛けています。金銭面では,研究室の同僚やレジデント時代の先輩方から,循環器救急当直やICU当直などの外勤先を紹介していただき,約6~8回/月ほど研究に支障のない範囲で臨床業務を続けています。
今回の国内留学に際して,大石教授には多大なるご尽力をいただきました。また,多くの同門の先生方のご協力により,このような素晴らしい機会をいただいております。この場を借りて御礼申し上げます。引き続き,良好な研究成果を出すため尽力してまいります。
2. 小倉記念病院 循環器内科
末永智大
皆様ご無沙汰しております。2019年入局の末永智大です。大石教授と小倉記念病院白井伸一先生のご縁により,2023年4月より小倉記念病院に国内留学の機会をいただき,日々国内有数の治療件数を誇る大動脈弁狭窄症に対する TAVIや,僧帽弁閉鎖不全症に対するMitraClipやPASCALを使用したM-TEERなどstructure heart disease (SHD)を中心に勉強しております。
小倉1年目はhigh volume centerのスピード感に慣れず,体重減少に悩まされる日々でしたが2年目に突入し,徐々に小倉の生活にも慣れてきました。今年度より規定の条件に達したため,PCIに関しては術者として多くの症例を経験させていただいております。TAVI後PCIや石灰化病変など複雑病変も多く,日々勉強になっております。
また,診療のみではなく臨床研究も重要視されている当院では,若手のモチベーションが非常に高いのも特徴です。研究面に関して全くの素人でしたが,猛烈な勢いでSHD診療と論文執筆を行なっているメンター的存在の上司に(強引に)弟子入りし,昨年度は症例報告をJACC case reportに掲載できました。最近は単施設の TAVIについての臨床研究の論文を執筆しsubmitしております。多施設レジストリーへの参加もあるため,今後も無理のない範囲で積極的に論文執筆してまいります。
当院のように同世代の医師が日常的に論文を執筆している環境に身を置くことは非常に貴重な経験です。臨床研究に関しては診療面以上に半人前で独り立ちには程遠い状況ですが,たくさんのことを吸収し,鹿児島の同世代の先生方へ日常診療を行いながら論文を執筆するtips的なものをなんとか持ち帰ろうと思います。
今こうして,身も心も線の細い自分が国内留学を継続できているのは,家族の応援あってこそだと感謝しております。医者人数も多くon-offがはっきりしているため,家族との時間も多く取れるのが幸いです。自分の小倉学年と同級生の2歳を迎えようとしている次女は,多くを語りませんが(心配です),一人歩きし意思をはっきり伝えるようになりました。まだまだ次女のように,診療面も研究面も自分の色を出せておりませんが,一歩一歩努力してまいります。
そして最後になりますが,貴重な機会を与えていただいた大石教授をはじめ医局員の皆様には深く感謝申し上げます。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
3. 宮崎市郡医師会病院心臓病センター 循環器内科
河合正太郎
いつも大変お世話になっております。2022年度入局の河合正太郎です。昨年度より宮崎市郡医師会病院循環器内科で後期研修医として学ばせていただいております。約1年半が経過し,日々の診療に携わりながら多くの経験を積ませていただいております。
本年度は,不整脈,心エコーのローテーションを終え,現在は虚血性心疾患を中心としたチームに所属し,若手医師としての責任と成長を実感しています。特に,CAG 200件のノルマを終え,待機的PCIのオペレーターとしてデビューできたことは大きな一歩であり,徐々にですが自信を持って手技に取り組めるようになりました。上級医の先生方の的確な指導やサポートのおかげで,多様な症例を通じて技術を磨くことができ,充実した日々を送っています。
また,柴田先生の「総合的に診療できる循環器内科医を育てたい」というご意向のもと,今年度も引き続き多分野にわたる基礎を学ばせていただき,知識の幅を広げることができました。現在は,学んだ内容を活かしつつも,さらなる専門的な知識とスキルの向上を目指し,臨床に励んでいます。症例やデータの豊富なハイボリュームセンターでの経験を生かし,少しずつ臨床研究に取り組むことができるようになってきました。少しでも成果を発表していければと考えています。
大石教授をはじめ,医局の皆様にご支援いただき,心より感謝申し上げます。ここで得た知見や技術を鹿児島の医療に還元することを目指して,これからも成長を続けてまいります。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
4. 国立循環器病研究センター 心臓血管内科 肺循環科
赤尾光博
皆様ご無沙汰しております。2017年入局の赤尾 光優と申します。
大石教授のご厚意により,2024年4月から国立循環器病研究センターの肺循環科の専門修練医として学ぶ機会を頂きました。
当センターは,循環器疾患の究明と制圧のために設立された国立高度専門医療研究センターであり,同建物内に病院,研究所およびオープンイノベーションセンターの3つの機関が存在し,循環器疾患の予防,診断,治療法の開発,病態生理の解明を推し進めています。一方で教育にも力を入れており,毎年レジデントや専門修練医といった立場で多くの医師が最先端の医療を学びに来ています。
肺循環科は当センター設立時に創設され,肺循環(肺高血圧症,静脈血栓症,成人先天性心疾患,様々な肺血管や静脈血管の病気)の分野の診療において大きな役割を果たしています。学ぶ側の立場からみても,科全体で毎週20名ほどの入院があり非常に症例数は豊富で,短期間であっても多くの診療経験を積むことができます。また,平日は毎日カテーテル検査・治療がありますので手技を学ぶうえでもメリットが大きいと感じています。経皮的肺動脈形成術についても年間200件程度の実施数があり,専門修練医も指導を受けながら術者として行うことが可能です。
臨床の中で個人的に印象に残った症例として,若い重症の特発性肺動脈性肺高血圧症の方がNO負荷試験のresponderであり,カルシウム拮抗薬単剤で著明に血行動態が改善した症例がありました。知識として持っていても実際にresponderの症例をみるのは比較的稀で,NO負荷開始後,数分も経過しないうちに肺動脈圧の波高が劇的に変化したことを目の当たりにし,大変驚いたことを覚えています。百聞は一見に如かずという言葉通り,非常に貴重な経験をさせて頂きました。
最後になりますが,このたびの国内留学の機会を与えてくださった大石教授をはじめ同門の先生方には深く感謝申し上げます。今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。