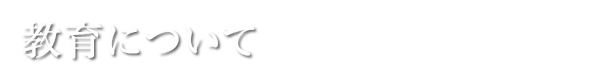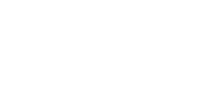研修医の方へ
留学生便り
バックナンバー(2018年)
国内
1. 桜橋渡辺病院 不整脈科
二宮 雄一
皆様,ご無沙汰しております。平成11年入局の二宮です。
平成29年4月より,大石教授が以前在籍されていたご縁で,大阪梅田にある桜橋渡辺病院でアブレーションを中心に勉強をさせて頂いております。桜橋2年目となり,不整脈科部長の井上耕一先生のご配慮で,主術者としての症例を経験させていただく機会も増えてきました。3Dマッピングシステム,心腔内エコーを用いることで,アブレーションの手技時間,透視時間が短縮していくことを日々実感しております。
治療のストラテジーは心房細動に対して,発作性,持続性にかかわらず「durable PVI (再伝導しない頑丈な肺静脈隔離) 」が基本です。持続性心房細動の症例に関しても,PVIのみで1年のフォローアップで約70%の症例が洞調律をキープできていることに驚きを感じております。
当院の特徴はアブレーション (2017年は842例,その中でAF 698例,クライオ 142例) ,PCI (2017年は932例) などの症例数の豊富さですが,もう一つの特徴としては盛んな学会活動,論文発表などが挙げられます。私もこのような環境下で刺激を受けつつ,井上先生のご指導のもと,日循総会,不整脈学会,ESC等で発表の機会をいただき,大変貴重な経験となっております。
私生活はというと,なかなか時間の確保が難しいですが,ランニングをしています。昨シーズンは神戸マラソンに出場し,今シーズンは井上耕一先生とともに大阪マラソンに出場しました。また,関西は子供達が喜ぶスポットも豊富で,和歌山のアドベンチャーワールドや,三重の鈴鹿サーキットなどに行くことができ,家族にも好評でした。
大石教授をはじめとする医局の先生にはこのような貴重な勉強の機会をいただいていることに大変感謝しております。少しでも多くのものを吸収して鹿児島の不整脈患者さんの治療に貢献できるよう頑張りたいと思います。今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
2. 京都大学 社会健康医学薬剤疫学分野
川添 晋
ご無沙汰しております。平成13年度入局の川添です。平成29年4月より京都大学社会健康医学薬剤疫学教室で勉強させて頂いております。
当教室は,臨床疫学及び薬剤疫学研究を主導すべく2000年に設立された講座です。教授の川上先生は45歳とお若いですが,既に同教室を10年以上率いておられます。全国から医師以外にも様々なバックグラウンドの方が集まっており,年齢も,人種も,言語も多様です。
臨床研究においては,レセプト,電子カルテ等のビッグデータを用いて臨床上の疑問にアプローチするというユニークな手法を取り入れております。エビデンス構築の一翼を担う分野として注目されており,国の法整備とあいまって今後さらに発展する分野と考えられています。
川上教授が主導されている,全国自治体の学校健診及び母子保健データのデータベース化及び連接事業にも携わっております。最初はお手伝い程度だったのですが,最近では労力の大部分を本取り組みに割いている状況です 。
全国から当教室に来ている医師の中で,循環器内科医は麻酔科につぐ勢力です。循環器内科は所見や検査結果が比較的数値化しやすいことにもよるのでしょうか。疫学や医療統計の専門家だけでなく,他大学の循環器内科の先生達と仲間になれたことも非常に大きな財産だと思います。このつながりを大切にしていきたいと思います。
京都は7月に国内最高の39.8度を記録しましたが,気候は想像以上に厳しいです。街中に出れば外国人と修学旅行生でもみくちゃになります。しかしその深い歴史と四季折々の風情はやはり格別なものがあるように思います。
最後に,貴重な機会を与えて頂きました大石教授をはじめ医局員の皆様に深く感謝申し上げます。
3. 琉球大学大学院医学研究科 臨床薬理学
徳重 明央
はいさい。皆様,ご無沙汰しております。
沖縄3年目となり,すっかりウチナーンチュ気分です。安室奈美恵の引退により意気消沈中にチャーミー襲来により宿舎のベランダの間仕切りが全て吹き飛び,ついでに車のサイドバイザーも吹き飛びましたが,なんとか私のクビは飛ばずに仕事が出来ていることに感謝の日々です。
ワークショップやフェローシップ,医学生,大学院生の指導などは継続していますが,今年はいくつか大規模研究が無事に終了しました。鹿児島大学病院を始め県内の様々な施設の先生にご協力をいただいた心房細動患者のコホート研究ですが,8000例登録完了いたしましたので,ご報告と感謝申し上げます。また,アナグリプチンとシタグリプチンのLDL低下作用を直接比較したRCTも完了し,論文投稿中です。CHD (冠動脈疾患糖尿病合併患者) コホートという10年に及ぶ経時的データを8000例近く固定し,主解析,サブ解析とも携わりいくつか報告予定です。
私生活では厄年のためか,通っていたゴルフ練習場がモノレールの延伸工事の立ち退きに遭い閉鎖されたり,車がレンタカーにぶつけられたり,ゴルフが上手くならないといった悲劇がありましたが,何とか1年経過しそうです。
臨床研究,生物統計に関して研鑽を積んでおりますが,来年度は帰鹿し臨床研究が盛り上がっていくよう頑張って行く予定です。あと少しですが沖縄にお越しの際はぜひお立ち寄りください。
最後になりますが大石教授はじめ,様々な先生にご協力いただき,深謝致します。今後ともご迷惑をお掛けいたしますが,引き続き御指導よろしくお願いいたします。
4. 国立循環器病研究センター病院 心臓血管内科部門
鮫島 光平
平成28年入局の鮫島光平と申します。入局後,鹿児島大学病院・鹿屋医療センターでそれぞれ1年勤務いたしましたが,このたび平成30年4月より国立循環器病研究センターで心臓血管内科ラウンドコースのレジデントとして国内留学の機会をいただいております。
当院は大阪府吹田市の千里丘陵の一角に所在しています。閑静な住宅街に隣接しており,近くには万博記念公園もありますので緑豊かな環境の中にあります。病院の総病床数は612床で,診療部門は心臓血管内科部門,心臓血管外科部門,脳血管部門,小児循環器科・周産期部門,生活習慣病部門,移植部門などがあり,その中でも私が所属する心臓血管内科は冠疾患科・血管科・心不全科・肺循環科・不整脈科に分かれています。心臓血管内科レジデントコースはこれら5グループおよび,移植部門・CCUを3ヶ月毎にローテートするかたちで研修を行っていきます。
レジデントの主な業務は病棟患者さんの診療と検査dutyの2つからなります。前者では指導医の先生とペアで担当症例を受け持ちます。病歴・病態が複雑な患者さんが少なくなく,アセスメントや方針決定に難渋することが多いのですが,日々のカンファレンスで実際にガイドライン策定に携わっている先生方はじめ多くの先生方に直接ご指導・アドバイスを頂けますし,問題の解決策も外科的介入,デバイスや移植も考慮されるなど多岐にわたりますので大変多くのことを学び,実際に患者さんのアウトカムにつながっています。後者の検査業務は,心エコー検査 (二年次からは経食道心エコーも),心臓カテーテル検査 (CAG,心不全カテ,三年次からはPCI),トレッドミル検査,運動負荷心筋シンチ,心肺運動負荷試験 (CPX) ,心臓リハビリテーションなどを適宜指導を受けながら行います。如何にこれまで勉強不足であったかを痛感するとともに,検査結果の意義について深く考察する機会が得られ,大変勉強になっています。また,研究に関しては多くのレジデントの先輩方がESC,AHAといった学会で発表をされており,優秀な先輩方と比し自身の至らなさを痛感している毎日です。
大石教授よりかつて「1日1つ新しいことを学んでいきなさい」と教えて頂いたことが記憶にあります。日々1つ1つ学んでいき,今回の留学の間,鹿児島でご尽力されている先生方や,何より鹿児島の患者さんへ還元できるように精進していきます。
2018年6月の大阪府北部地震では,センター建物の損壊がありましたが,地域の病院の力添えもあり早急な復旧が可能でした。自宅も停電・断水などなく特に大きな被害はありませんでした。2019年7月にはJR岸辺駅に隣接する新病院への移転が控えていますので,来年はさらに大忙しとなるかもしれませんが,末端のレジデントとして尽力できればと考えております。
5. 大阪大学医学部附属病院 循環器内科
山口 聡
ご無沙汰しております。
平成29年度入局の山口と申します。平成30年4月より,大阪大学医学部附属病院循環器内科で主に心不全について勉強をさせて頂いています。
当院の循環器内科は特に重症心不全診療に積極的に取り組んでおり,循環器内科病棟50床の中で半分以上を心不全の患者が占めています。心不全部門,虚血部門,不整脈部門,SHD部門,ACHD部門とグループ化されており,互いに連携して診療を行っています。2017年に入院した心不全患者の基礎心疾患は,特発性拡張型心筋症94例,虚血性心筋症33例,肥大型心筋症27例,弁膜症28例,急性心筋炎6例,感染性心内膜炎2例でした。
普段は心不全の原因精査や心臓移植登録申請,及び種々の重症度の心不全治療 (内科的治療から外科への橋渡しなど) ,植込み型補助人工心臓 (LVAD) 装着後または心臓移植後患者の自宅退院までの調整など,主に重症心不全患者の診療に参加しています。
LVAD装着患者を数多く診療していることが大阪大学の特徴の一つですが,それまで強心薬持続静注が手放せずに長期入院で安静に過ごしていた患者が劇的に改善し,自宅退院していく姿は非常に印象的でした。一方で,まれな合併症ではありますが,脳梗塞・脳出血を発症して後遺症を残したり,感染によりポンプ交換を余儀なくされるといった管理施設ならではの症例もみられ,適切な評価,対応の難しさ・重要性をいつも痛感させられます。
超重症の急性期の心不全患者の治療にあたる場合など,生きた心地が全くしない時もたまにありますが,多くの先生方,スタッフの方々に支えられながら,なんとか日々を乗り切っています。せっかくの大阪なので行きたいところは沢山ありますが,当面は診療と睡眠で一杯となりそうです。
2年間という期間で1つでも多くのことを学び,鹿児島に帰ったときになんらかの形でお返し出来ればと思います。貴重な勉強の機会を与えて頂きました大石教授をはじめ,医局員の皆様方に深く感謝を申し上げます。