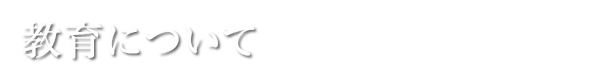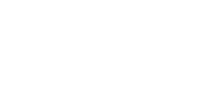研修医の方へ
留学生便り
バックナンバー(2017年)
国内
1. 桜橋渡辺病院 不整脈科
二宮 雄一
皆様,ご無沙汰しております。平成11年入局の二宮です。
平成29年4月より,大石教授が以前在籍されていたご縁で,大阪の桜橋渡辺病院でアブレーションを中心に勉強をさせて頂いております。
当院はJR大阪駅,阪急・阪神・地下鉄梅田駅から目と鼻の先にあり,全病床数171床は全て循環器病床です。柱としては,PCI,アブレーション,心臓CT,心エコーが挙げられます。2016年 (1~12月) の実績は,PCI 915例,EVT 95例,アブレーション817例 (このうちAFアブレーション 687例。AFのうちクライオアブレーション 146例) ,心臓CT 4340例です。
アブレーションは月曜日から金曜日の午前・午後行われています。不整脈科部長の井上耕一先生のご配慮で,アブレーションに専念しやすい環境を作って頂き大変有難く思っております。当院のアブレーションの特徴は,心房細動症例の多さです。発作性心房細動はクライオアブレーション,持続性心房細動は3Dマッピングシステムを用いたカテーテルを用いたアブレーションを行なっています。心房細動に対して,発作性,持続性に関わらず肺静脈隔離術を安全に,シンプルに,スピーディーに行うことが,基本的な考え方のようです。アブレーション以外には,エコー,救急外来,一般外来を担当させて頂いております。特に,エコーは経食道心エコーもさせて頂き,貴重な経験となっています。
自宅は梅田から北に地下鉄御堂筋線で20分の千里中央にあります。アクセスが良く便利で,大きな公園も多く,子育て環境がいいので家族も気に入っており安心しているところです。小児科医である家内は,豊中市内の病院で少しずつ働き始め,小学1年の長男はもうすっかり関西弁です。私はというと,最近健康づくりのためにランニングをしていますが,大阪にいる間に関西の大会にも参加できればと思います。
このような貴重な勉強の機会を頂いていることに日々感謝し,少しでも多くのものを吸収して帰れるよう,体に気をつけて頑張りたいと思います。今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
2. 京都大学 社会健康医学薬剤疫学分野
川添 晋
ご無沙汰しております。平成13年度入局の川添です。平成29年4月より京都大学社会健康医学薬剤疫学教室で勉強させて頂いております。
当教室は,臨床疫学及び薬剤疫学研究を主導すべく2000年に設立された講座です。川上浩司教授は現在44歳とお若いですが,既に同教室の教授を10年間つとめられています。教室には全国から様々なバックグラウンドの方が集まっています。医師,薬剤師,他学部の研究員 (理,工,経済学部) ,製薬会社の研究員など職種だけでなく,人種も,年齢も多様です。
研究内容としては基礎研究から臨床研究まで広範囲に渡りますが,臨床研究においては,臨床上の疑問に対してリアルワールドデータ (レセプト,電子カルテ,薬局処方など) を用いてアプローチするというユニークな手法を取り入れております。従来のRCT中心のエビデンス構築に加えて,今後はコンピューターを利用したビッグデータ解析による研究が進むと推測されます。本年の個人情報保護法の改正や総務省の条例改定勧告など,既存データの利活用については国も推進しているところで,今後さらに発展する研究分野と思われます。後ろ向き研究というとお手軽な印象ですが,前向き試験にはない困難があります。交絡を取り除いてより真実に近づく必要がありますが,そのためには緻密なデータハンドリングと,適切な統計手法の選択が必須です。ここが非常に難しい反面,おもしろくもあるところです。
川上教授がライフワークとされている,全国の学校健診及び母子保健データの可視化及び連接事業に関してもお手伝いをさせて頂いております。自治体の教育委員会や健康福祉部とのやりとりが中心です。これまでとは違った仕事でとまどいもありますが,何とかやっています (法律や条例の内容のやりとり,弁護士との相談など…素人なりにですが) 。
気付けば京都での生活も半年が過ぎ,紅葉が見ごろを迎えています。春の一面の桜も見ものでしたが,この時期の京都の山々の彩りはそれはもう圧巻です。見るところには事欠きませんので,お近くにお越しの際にはぜひお声かけ下さい。
最後に,貴重な機会を与えて頂きました大石教授をはじめ医局員の皆様に深く感謝申し上げます。一つでも価値あるものを持ち帰るべく勉強いたします。
3. 琉球大学大学院医学研究科 臨床薬理学
徳重 明央
はいさい。皆様,ご無沙汰しております。
沖縄に来て早いもので1年半が経過しました。
年6回ほどある臨床研究インテンシブフェローシップや慈恵医大との合同春季ワークショップ,琉大主催の夏季ワークショップ,その他日本循環器学会や日本高血圧学会の臨床研究ワークショップに参加する機会があり,臨床研究の企画・立案から実行,統計解析までのグループワークを参加者と一緒に勉強することができました。慈恵医大,兵庫医大,国際医療センター,東北大学など様々な場所からいらっしゃる講師陣に御指導いただいており,意識の高い参加者にも刺激を受けております。さらに,臨床研究管理学講座での大学院生 (30名近く!) との研究合宿,中部病院での出張研究相談など,毎月イベントが目白押しです。
今年の成果としては県立中部病院の放射線技師さんの修士卒業と論文作成,FMD-J研究というFMDと心血管予後との関連を調査している多施設研究から論文がアクセプトされ,鹿児島大学在籍中に行った前向き観察研究の結果をまとめ論文公表を行うことができましたが,研究費獲得のための計画書作成が非常に重要であることに気づいた年でもありました。植田教授のおっしゃるattractiveな文章を書くのは感性と日本語力の問題もあり,私の力不足を痛感しております。
また,琉球大学主幹の研究としてNOACs studyという非弁膜症性心房細動患者を登録していく観察研究を急ピッチで行っておりますが,鹿児島大学病院を始め県内の様々な施設の先生方にご協力をいただき誠にありがとうございました。CHDコホートという糖尿病合併冠動脈疾患患者を10年近く追跡した前向き観察研究では,目標の8000症例登録完了し,2018年の日本循環器学会のLate breaking cohortやシンポジウムで結果を公表予定です。
私生活では,家族は小学校などの関係で鹿児島へ引っ越し,今年度から単身赴任状態ですが,昨年末よりゴルフにどっぷりはまり,沖縄の海には目もくれず,芝生を駆け回るようになっておりますが,なかなか上達しないのが目下の悩みです。
臨床研究,生物統計に関して研鑽を積んでおりますが,鹿児島でも臨床研究が盛り上がっていくよう頑張って行く予定です。沖縄にお越しの際はぜひお立ち寄りください。
最後になりますが,大石教授はじめ,様々な先生方にご協力いただき深謝致します。今後ともご迷惑をお掛けいたしますが,引き続き御指導よろしくお願いいたします。