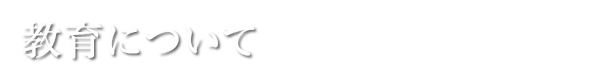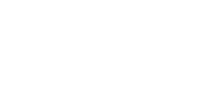研修医の方へ
留学生便り
バックナンバー(2015年)
国外
1. Mayo Clinic, Cardiorenal Research Laboratory
市来 智子
皆様,御無沙汰しております。今年は大分暖かい冬を迎えたミネソタから御報告させていただきます。もうすぐアメリカに留学し8年になります。長く居れば居るほど楽になるかというと全くそうではなく,次々と新たに課される困難に直面しています。お蔭様でこちらにいた実績を評価して頂き,11月1日をもってメイヨークリニック内科の准教授に昇進することができました。今後も更に成長できるよう,精進していく所存です。
最近は実験・臨床研究・論文執筆や研究費獲得のための申請だけでなく,共同研究や講演などを介して内外の人脈を広げるような活動が多くなってきました。なかなか英語の名前を覚えられないのと,もともと初対面で長時間話すのが得意ではないのに加えてつたない英語を駆使しなくてはならず,四苦八苦しながら時には胃が痛くなる毎日です。出張も増え,ラボでの仕事も増えているので,たまには家でのんびりしたいなとミネソタの美しい四季を横目にみながら感じています。
研究は心腎連関の病態生理と重症心不全患者の治療開発に焦点をしぼって行っています。特に重症心不全患者の研究はベッドサイドと連携していますので,楽しく感じます。特に治験関連になると研究費が膨大にかかるため,この先は自分でNIHやAHAから資金を調達しなければならず,越えなければならない壁は大きいです。
最後になりますが,皆様の御健康とより良き未来を心より祈念いたします。
2. Stanford University Division of Vascular Surgery
古庄 優子
皆様ご無沙汰しております。平成12年入局の古庄優子です。
私は2013年4月より,アメリカカリフォルニア州スタンフォード大学血管外科に研究留学をしています。
スタンフォード大学は,サンフランシスコから南へ約70km,パロアルトという街にあります。私が属するDalman Labでは,主に腹部大動脈瘤に関する研究を行っており,マウスの大動脈瘤や動脈硬化モデルを用いて動脈瘤に関連する遺伝子を研究しています。
私は,Hypoxia Inducible Factor 2α (HIF-2α) が大動脈瘤形成に及ぼす影響についてと,Basic leucine zipper transcription factor (BATF) に関する研究を行っています。手術でマウス動脈瘤モデルを作成し,腹部エコーで腹部大動脈瘤の形成過程を測定するのですが,スタンフォード大学の共用施設には動物専用の40 MHzプローブや麻酔吸入器などが充実しているため非常にありがたいです。
これまで日本でやっていた研究とは異なる内容でしたので,留学後しばらくは実験も論文も理解出来ず大変でしたが,HIF-2αについては幸いなことに2015年5月にサンフランシスコで開催されたATVBでポスター発表させて頂くことが出来ました。BATFにつきましては,ApoE欠損マウスとのダブルノックアウトマウスを作成するのに思いがけず時間がかかってしまったため,予備実験のみを行い,残りは後続の方に引き継ぐことになりそうです。全て予定通りというわけにはいきませんでしたが,後悔の無いようできる限り頑張りたいと思っております。
留学をするにあたり,お世話になりました医局の皆様に心から感謝申し上げます。
国内
1. 桜橋渡辺病院
薗田 剛嗣
ご無沙汰しております。医局の皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。2015年4月より桜橋渡辺病院へ留学させて頂いておりますので,近況をご報告申し上げます。
桜橋渡辺病院は,1967年に大阪『キタ』の玄関口である梅田に創立されました。現在は161床の循環器に特化した病院です。医師数は循環器内科19名 (うち1名は放射線科兼任) ,心臓血管外科5名 (院長を含む) ,消化器外科1名,麻酔科2名です。
経皮的冠動脈インターベンション (PCI) は1984年10月1日に当時在職されていた加藤修先生が開始されて以来,ここ10年間は藤井謙司副院長,岡村篤徳部長 (冠疾患科長) を中心に年間延べ700人の患者さんへ治療を継続しています。また,近年ではカテーテルアブレーションにも積極的に取り組んでおり,井上耕一部長 (不整脈科長) を中心に昨年は600件以上施行しています。
PCIを深く勉強したいという私の希望を大石教授が汲んで下さり,先生ご自身が若かりし頃に修練を積まれた桜橋渡辺病院への留学を叶えて下さいました。現在,午前中は一般外来や救急外来,ICU当番や心エコーを曜日毎に担当し,午後からカテーテル室にこもる日々です。自分が術者としてPCIを行う際には岡村先生について頂き,細部に至るまでご指導頂いております。もちろん,助手にも積極的に入るようにしています。大石先生が在職されていた頃は今よりも忙しい中で,今よりもはるかに多くの論文執筆や学会発表をされていたとのことで,まだまだ努力が足りないと反省しております。
最後になりますが,私を支えて下さっている医局の先生方へ日々感謝しながら,鹿児島へ戻ったら少しでも戦力になれるよう,引き続き大阪で頑張りたいと思います。
2. 東京女子医科大学
吉村 あきの
皆様こんにちは。
2015年4月より,東京女子医科大学病院循環器内科に国内留学中の吉村です。
私がこの「留学生だより」を書く事になろうとは,入局した頃は夢にもおもわず,自分でも不思議な思いです。これもこのような機会があればこそですので,感謝の気持ちを込めて書かせていただきたいと思います。
私は東京女子医大に来て何をしているかと言いますと,「5番カテーテル室」なるEPラボで,不整脈のアブレーション・デバイス治療について主に学ばせていただいております。
東京女子医大は今まで諸先輩方も留学されており,庄田先生を筆頭とする不整脈チームです。庄田先生の電位・心電図を読む力や,経験に基づいた話は聞いているだけでも勉強になります。
また,デバイスにおいても東京で第2位の症例数をほこる病院ですので,手技から外来のフォローの仕方まで,今までの自分の未熟さを痛感する毎日です。
不整脈分野で,いつか鹿児島でもできたらと思うものに,ペースメーカーのリード抜去があります。ハイブリッドカテ室 (透視が使えるオペ室) で,心臓血管外科とも協力をしながら,開胸をしないリード抜去を数年前より行っております。植え込み後何年もたったリードも,メカニカルシースやレーザーシースを用いて抜去をします。ハイリスクの患者さんの場合,うまく抜ければ術後の回復が早く,高齢化著しい鹿児島に,リード抜去を持って帰れることを夢見て勉強中です。その他,先天性心疾患の患者のアブレーションなども見る機会もあります。他の分野においても,毎朝している医局員全員で持ち回りの抄読会があり,色々なトピックを聞くことができますし,かの有名な「心臓センター」がありますので,時々は最先端のことがでてきたりもします。
東京での生活ですが,私を知る方は東京で生きていけるのか心配されているのではないでしょうか。自分も不安だったのですが,おかげさまで無事に生きております。最初こそ,新宿駅でしょっちゅう迷子になり,右往左往しましたが,大好きなパン屋巡りをするために,スマホの力をかりて,目的地にたどり着けるようになりました。人ごみにもだいぶ慣れました。そうなると,東京はどこに行くにも便利で,各地の勉強会にも楽々なので,まめに足を運ぶようにしています。休日は,時々は関東近郊にも足を運び,尾瀬や北陸にも行きました。
留学自体はそろそろ終わりますが,私が勉強に行きたいと分不相応なことを言った際に,快く送り出してくださった大石教授をはじめ医局の皆様には,本当に感謝しております。特に,不整脈班の先生方には,過重労働をさせてしまい,申し訳ありませんでした。また,勉強に行く前に励ましてくださった先生方のお言葉も,留学中,大変励みになりました。この紙面をもちまして,お礼をさせていただきたいと思います。
大変勉強になった留学生活ですが,やっぱり慣れ親しんだ鹿児島に帰れることが楽しみでもあります。皆様に恩返しできる様になるには,時間もかかるかと思いますが,少しでも鹿児島の医療の向上の為に役に立てるよう,残りの留学生活を楽しみたいと思います。